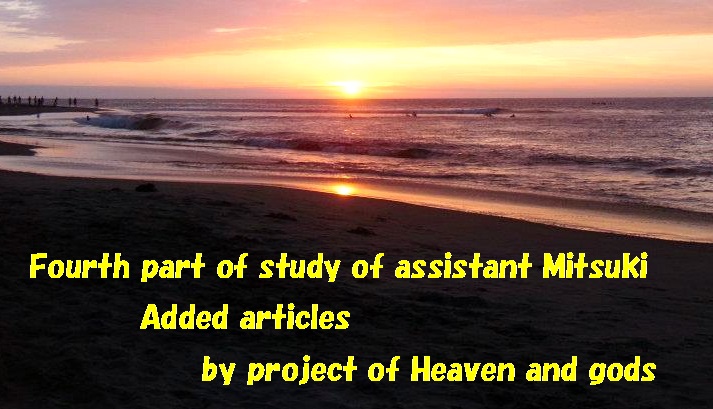GIOVANNI MARRADI - Children of Sarajevo (video inspired by god of star)
64 みつきの守本順一郎の思想史研究から受け取った個と共同性のテーマを最高のレベルまで高めた生涯にわたる思索の結果をまとめたものです
summarize of results of lifelong theme of individuality and cooperativity of Mitsuki received from Morimoto Junichiro's history research , which has been continued to deepen to highest level
This article is summarize of results of lifelong theme of individuality and cooperativity of Mitsuki received from Morimoto Junichiro's history research , which has been continued to deepen to highest level.
Morimoto is only true Marxist in 20th century.
Mitsuki's life is deepening true Marxism.
この論文は,みつきの守本順一郎の思想史研究から受け取った個と共同性のテーマを最高のレベルまで高めた生涯にわたる思索の結果をまとめたものです。
守本順一郎は20世紀の唯一の真のマルクス主義者です。
みつきの生涯は真のマルクス主義を深めつづけたものだったのです。
まえがき
拝啓
先生の以下のご指摘はもっともだと思います。
「サイードや工藤庸子に言わせると、マルクスも『オリエンタリスト』(英仏を筆頭とする帝国主義者がアジア等の異文化・異文明を『野蛮』として奇異な目で見る観点の人たち)の最たる一員です。
『まず西欧的(あるいは一神教的?)な個の自立、しかる後に共同』で良いのかどうか、問題だと思います」
個と集合体との関係性について、私の考えを説明しないと誤解されると思いますので、少し詳しく論じさせてもらいます。
(1)「必須の通過点」としての個の確立の意味
資本の本源的蓄積過程で小農民や職人が土地などの生産手段を奪われて、生産手段を所有する資本家に雇われるしか、生きてゆく道がなくなります。
これは資本主義が発展する過程では、世界中に見られる現象です。
資本主義の発展の中で機械の一部となって働かされる労働者は、もはや職人や農民であった時代にもち得たような主体性はありません。
マルクスは「疎外された労働」と呼びましたが、「疎外された労働」から解放されるためには、労働者たちが、働く職場の主人公とならなくなはなりません。
後にマルクスの「社会主義」理論は、生産手段の国有化として結実してしまいましたが、本来のマルクスの問題意識は、労働者たちが働く場で主人公になる。
すなわち主体性を回復することにあったとおもいます。
(P.R.サルカールは、マルクスのこの問題意識を継承し、経済民主主義を基本とする進歩的社会主義(プラウト)の理論を創始し、適切に解答を与えていると考えます。
さらにケン・ウィルバーのホロンとホラーキーの理論を用いれば、結局のところ、サルカールと類似の理論を創造することができます。
これについては、後で説明します)
「必須の通過点」としての個の確立を論じたのは、西洋で発達した資本主義システムとその文明を即美化するためではありません。
資本主義システムは、個の主体性の確立を奪うものだからです。
しかしながら、本源的蓄積過程、すなわち生産手段を所有している資本家に雇われるしかない多数の労働者が農村から析出される時点において、農民の主体性のレベルがどの程度あったかは、労働者階級に組み込まれた彼らが主体性を回復するために団結して闘う意欲に関連してきます。
資本家の側に組み込まれて、経営の発展や技術の発展に尽くす能力にも、本源的蓄積過程で労働者に転化する農民がどの程度の主体性をもっていたかは重要です。
実際、資本主義の発展過程を見ても、独立した小農民レベルに達した英米仏、ドイツの西側地域、それに対して地主制のあった東欧地域、日本も地主制があり、共同体規制はあるけれども、経営単位は小農民家族にありました。
私が調べていたイランのライーヤット(農民)は、経営単位は農民家族にありませんでした。
ラテン・アメリカのラティフンデオ(大土地所有制)も経営単位が農民家族になかったとおもいます。
朝鮮、中国、東南アジア地域での資本主義の発展が進んでいますが、経営単位は農民家族にあります。
これは実証の問題ですが、資本家と労働者が形成されてゆくに際して、彼らの個としての主体性のレベルが、影響してゆくだろうことは確実です。
そして地主支配からも解放されて、完全に自らの生活の主人公となった独立自営農民のレベルの主体性を「必須の通過点」という考えに共鳴します。
主体性をもった彼らのつくりだした文化の質は、次の資本主義段階で主体性を奪われた状況に対して抵抗する心を激励してゆくものとなるはずです。
(もちろん、一つの要因としてです。それが要因のすべてだと言っているのではありません)
たとえば、人気番組の水戸黄門で、繰り返し、権力者によって問題を解決してもらうという心性を教育されつづけている私たちの社会とはちがって、「必須の通過点」を経た文化は、水戸黄門のような外からやってきた善き権力者に問題の解決を期待するのではなく、その地域の人々が力をあわせることによって問題を解決する心性を育む文化を継承しているはずです。
(2)守本順一郎の思想史研究の意義
こうした私の問題意識は、故守本順一郎(元名古屋大学の思想史研究者)の思想史研究によります。
簡単に手に入る本は『日本思想史、上中下』新日本新書です。
彼は、マルクスの資本論に『個』としての自立が『必須の通過点』であるとしたことにならって、思想史における「個」の確立まで前近代史の思想史を研究して、この世を去りました。
その研究は、決して、「西洋的個の自立、しかる後、共同」という文脈からではありません。
まさしくそうした西洋は個が自立しているという単純な考えを批判するためでした。
「ヨーロッパの近代資本主義=帝国主義が、広大な範域を占める東洋諸国に資本主義=帝国主義的衝撃(インパクト)を与えるまで、たしかに東洋の世界は、外貌的には専制的支配の世界であった。
だが、上述のように、ヨーロッパ的精神の立場から東洋を停滞的社会として捉えることは、既に(自由)の精神を展開させえたと自負するヨーロッパ精神にとっては、そのような東洋の内容把握も、外からの、いわば好奇心から、瞥見にすぎなかった。・・・
かくして、古代から近代資本主義の時代、さらにいえば、最近の帝国主義段階に至るまで、ヨーロッパの精神は、東洋の本質をその内的発展において探るべき必然性を自己の裡にもたなかったといえるであろう」
守本順一郎『東洋政治思想史研究』未來社、1967年、10、11ページ
彼は、西洋思想、インド思想、中国思想について、個と共同性(ケン・ウィルバー的にいうとエイジェンシーとコミュニオン)の構造を発展のありさまを見事に普遍的に描きだしています。
共同体に埋没した個から、すなわちコミニュオン優位型から、次第に個が力をましてゆく様子を普遍的に、かつ地域的特性を描きだしながら、論じています。
前近代思想を論じていますが、私は、その中に自立した個の連合としての未来社会論を読み取っています。
そして自立個の成立は「必須の通過点」です。
もちろん、一人だけで成り立つような個はこの宇宙のどこにも存在しえません。
自立した個といえども、他者との関係性を前提としてのことはもちろんです。
具体的なイメージは、たとえば独立自営農民として「いつ、何の種をまき、どういう肥料をやり、いつ、刈り取り、市場に出すか」などについて自己決定権をもつということです。
地主や共同体の規制から自由に決定できるということです。
たしか、マルクスは、資本論の中で14世紀のイギリスに広範にヨーマンリーが成立し、彼らは、非常に狭い世界観の中ではあるけれども、独立した小宇宙をつくっていたことなどを論じていたとおもいます。
自己決定権をもっていた小農民が、資本主義の発展の中で、生産手段を奪われ、自己決定権を失った労働者として働かされるようになります。
そして資本主義が発達させた生産手段を労働者たちがわがものとして、生産における自己決定権を回復します。
これが資本論の論理でした。
つまり、主体的な個が協同の上に成立するのです。
この個とは共同の中に埋没する前近代的な個であってはなりません。
ソ連、中国、北朝鮮に、社会主義と名付けた統制経済が登場しましたが、それは集団に埋没した前近代的な個を前提としていました。
それは、「必須の通過点」として個の自立を経ずに、上から共同を押しつけた悲劇?でした。
マルクスのイメージはどう考えても、独立した生産者が、いったん生産手段を奪われる資本主義がやってくる。
そこでその生産手段をふたたびわがものにするというものです。
つまり自立した「個」を前提としているのです。
それは経済民主主義でもあります。
それなしには、全体主義や専制支配となってしまいます。
その意味で「自立した個」の成立は必須の通過点として、社会の前進の上でも個人の成長の上でも必要なことだと私は考えています。
(サルカールの進歩的社会主義(プラウト)は、まさしく、主体的な個の協同として、協同組合を基本とした組み立ての社会を構想しています。
そして経済民主主義を主張しています。
マルクスのもともとの労働者解放の問題意識を正当に継承し、その解決の展望をあたえているように私はみえます)
(3)一神教世界での個の発達
経済的側面から、個の確立という「必須の通過点」について述べました。
心の外側は内側に対応しています。
今度は内側を考えてみましょう。
守本順一郎は、一神教世界だから、個が確立したような短絡的な見方はしていません。
簡単に言います。
ギリシャ・ローマ(古典古代)の原始キリスト教段階では、奴隷は、この世で個として認められません。
死んで天国に行って救われます。
中世カトリシズム段階では、個はこの世で人間として認められますが、神に近い人間と神から遠い人間、人間以外の異端者や魔女というふうに位階制(身分制)が形成されます。
教会は高く天(神)に向かってそびえたちます。
個が自立できない背後には、領主支配と共同体規制の中で個別家族が成立するという事情が対応しています。
次にプロテスタンチズムがきます。
個と神とは直接につながります。
すなわち個は神の前で平等になります。
勤労してもうけることは神を讃えることになりますから、資本主義が発展します。
資本主義の発展の中で、個の自立はくずれてゆきます。
少し、私の解釈が加わっていますが、一神教世界でも歴史的な展開があったし、私たちの多神教世界でも歴史的な展開がありました。
したがって、言いたいことは、一神教的な個の自立を経たらいいという単純なことではないのです。
(4)内的世界でも重要な個の確立と自己決定権
依然として「必須の通過点」としての個の確立は、つまり確立した個の連合への道は私たちの社会の課題であるように思えます。
ヨーマンリーを例にとりましたが、知的世界でも「自分の研究畑で何をどのように研究するか」について自己決定権があり、その連合としてのアカデミズムの世界が発展すべきだとおもいます。
しかし、昨今の流れをみてみますと、政界や財界に学問界が従属しつつあるようにみえます。
本当に学者が自由に自分の畑で何をどのように研究するかについて自己決定権を維持できているのかが問題だとおもいます。
もちろん理科系の学問など現実の産業界との関係を軽視することができないのはよくわかりますが、たとえば、食品添加物の心と身体におよぼす害にいて研究しようとすると産業界がバックアップしないし、抑圧してくるだろうということは素人でもよくわかります。
学問界と産業界との関係ではありませんが、最近、人気があったテレビ番組「白い巨頭」では、江口洋介扮する医者が、本当のことを証言したら、妻への「世間」(大学教授の妻の会)から圧力がかかる様子を描いていました。
江口洋介扮する医者は、大学を追われて、自分の研究テーマが継続できませんでした。
そこまでのことはないにしても、今日も似たようなことがありうることは予想できます。
「自立した個の協同」というテーマは、今日のテーマでもあります。
個が自己決定権をもつことができるということを前提とした協同を実現することは、たいへん重要なことです。
それなしの協調は、容易に「体制順応型優等生」の協調になります。
洗練はされていても実質的には、個が集団に埋没した共同体です。
上からの支配を容易に許してしまいます。
内面的な側面について、さらに論じますと、理論と実践の統一は、個としての主体性の問題でもあります。
理論信仰になって、ある図式や理論的枠組みを、リアリティをより深く認識するために使うのではなく、理論自体を理解するために使う。
ここには個としての主体性はありません。
逆に理論を軽視して、実践だけを追求することは、暗に、その実践を指示しているもののいいなりになってしまいます。
どちらにしても、個は流されてゆきます。
この問題は日本の教育にもあるとおもいます。
優等生は、教えたことをそのまま受け入れて、記憶して、答案に書きます。
教えられたことをリアリティによって検証する実践にあたるものがありません。
だから教えられたことを真の意味で発展させることができません。
そういう優等生が、教育の仕事についても、容易に上から点数をつける制度である「評価・育成システム」の支配の目にからめとられ、行政からの採点に左右されるだろうとおもいます。
実践と理論を車の両輪のようにして自分の教育実践を発達させるスタイルの主体性をもったものはわずかしかでてこないでしょう。
調べてみると「優等生」の意味内容を含むものは英語の辞書にはありませんでした。
個の主体性をもった優秀な人物は、日本語では優等生とはいわないとおもいます。
盛んに教育界で、「個性」尊重とか多様化とかいいます。
私は多様性の尊重は、根源が一であるという意識、多様性の中に自分があるという意識が同時に育まれるならば、価値あることだと思います。
多様性の尊重の側面だけが推進され、自分にとって多様な他者という認識に留まるならば、自立した個(多)の連携(一)には進みません。
そして「個性」尊重と「個の確立」とは別のことです。
個性の尊重自体が個の確立に導くわけではありません。
個の確立、個の主体性の育成には、自分が耕す畑をもち、自己決定を行使することが重要です。
主体性は、自分の担当領域を与え、自己決定権を与えなくてはでてきません。
他人を利用しよう、操作しようという意図をもっている人間は、それを妨害してくるとおもいます。
(5)内面世界での個の確立を必須の通過点として論じはじめたケン・ウィルバー
ケン・ウィルバーは、『統合心理学』春秋社、において、個人の内面の発達においても、言葉は違いますが、事実上、個の確立を必須の通過点として強調しはじめています。
そしてトランスパーソナル心理学の理論家の一員であった段階から、まったく新しい人類的な思想の提出者となりつつあります。
彼は、偉大な叡知の伝統の目立つ欠陥に眼をふさぐことなく、その欠陥をとりあげなくてはならないと述べ、その欠陥の一つとして、「個」を消すことには導くが、「個」の確立に導かないことをあげています。
「強い安定した自我」の確立を人間発達の必須の通過点としているのです。
「偉大な観想的な伝統は、人間の成長の、心的で自我的なモードから超・心的でスピリチュアルなモードへの移行の洞察については非常にすぐれている。
しかし、心的・自我的なレベルへ達するまでの理解に関しては、非常に弱いものがあった。
ジャック・エンゲラーはいみじくも言っている。
「誰でもない、無の人になるためには、その前に誰かにならなくてはならない」(無私の前に私が来なければならない)強い安定した自我をもってはじめてそれを超越することができるのである。
偉大な叡知の伝統は、後の部分には見事に成功しているが、後の部分にはみじめに失敗しているのである」
ケン・ウィルバー著『統合心理学』春秋社、2004年、49ページ。
なお、叡知の伝統とか、観想の伝統というものは、キリスト教、仏教、イスラム教などの宗教的伝統の黙想的な部分をさしています。
個と集合体とのかかわりのテーマを内面的な発達の領域で見た場合、私たちの社会が直面しているのは、肥大化した個です。
お金や出世でコントロールするシステム、消費文化のコマーシャル、それは、物質的領域への我欲の肥大化です。
それは、心の奥に満たされない渇望を生みます。
癒しや仏教ブームの背景にあるものだとおもいます。
人権や差別反対のリベラリズムは、継承してゆかねばなりませんが、この満たされない渇望に対しては無力です。
より高次の渇望に組み替えてゆく以外に道はありません。
それは個を「含んで超える」道に解決があります。
「超える」個ですから、「超個」=トランスパーソナルです。
それを提起しているのがケン・ウィルバーです。
宗教の中の黙想的伝統は、「人間はパンのみにて生きるにあらず」と物的欲望をより高次なスピリチュアルな欲望に変える力をもっています。
しかし、個を消滅させる導き、すなわち個を超える導きには強いが、個を確立する点で弱いといいます。
それは専制的な上から支配する社会システムを容易に受け入れる人々を生み出します。
真にトランス、すなわち個を「含んで超える」ものでなくはなりません。
(そして二つ目の叡知の伝統の弱点として、それがまったく社会経済的側面を問題にしない点をあげています。
このことが、宗教が、保守的な人々、上からヒエラルヒー的に支配される社会システムを容易に受けいれる人々を数多く生み出し、リベラリズムに敵対するものとなっている背景にあるとウィルバーは考えます)
そして、トランスパーソナル心理学の人々とかつての自分は、「個」として確立する以前の「前個」を「超個」と勘違いしているとして前個⇒個⇒超個、すなわち「個」の確立を必須の通過点とすることを個人の内面の発達の上でも重視する立場を論じています。(同上書263ページ)
ケン・ウィルバーは、「自分の究極の関心事」の深まりと広がりの発展をスピリチュアリティの発達ラインとしています。
自分のことだけに関心がある領域から、分別のある理性の段階に達するのが個の段階です。
そして全人類的な運命が自己の関心事までに達した段階は、超個の高い段階に達しています。
スピリチュアリティの発達における「超個」とは現世から去ることではなくて、現世を「含んで超える」深まりをもつことです。
そして「自立した個」「主体的な個」を「含んで」超えていることです。
したがって、「超個」に発達した人間が増えれば、増えるほど、「自立した個」の共同、連携が発達してゆきます。
(6)マルクスの資本主義批判の限界
人々の出世と物欲をあおることを、今日の資本主義はその存在の必要条件としています。
それは人々を「超個」には導きません。自立した「個」のレベルの人々も出世競争の中にまきこまれ、この世での高い社会的地位の確立に執着します。
「前個」のレベルの人々もゆがめられてゆきます。
そこからスピリチュアリティへのがれようした一部の人々は、「個」としての主体性が、消滅させられ、崩壊させられてゆきます。
それがオウムです。
また宗教に走る人々も、ケン・ウィルバーの言うように、その保守性に取り込まれ、「前個」の受動性の中に取り込まれます。
したがって出世競争と物欲をあおる資本主義システム維持の基盤になります。
マルクスの資本主義批判は、労働者階級の資本家階級への階級闘争にあります。
まず労働条件などの向上の要求ために労働者階級として団結します。
そしてその中から育ってくる活動家は、労働者階級に奉仕することで無私の精神を発達させ、「個」の確立と「超個」に至ることになっています。
この場合、二つ問題があります。
労働運動の基盤は、労働条件の向上という物的要求に根ざします。
それは当然のことで、正しいことです。
しかし、その後に問題が二つあります。
その一つ目の問題は、その意識を階級意識に高めることを目標としています。
それは労働運動の発展、すなわち労働者階級の団結のためには必要なことですが、階級意識を普遍的意識に高める論理と実践が必要です。
物的要求を知的欲求にそしてそれを含んで超えたスピリチュアルな人間発達の要求に高める論理と実践です。
それがないと労働者は労働条件の向上を実現した後は、目標がなくなり、他民族の帝国主義的支配のイデオロギーにも容易に乗せられてゆきます。
逆に、もし、労働者階級が階級意識に目覚めなかったら、物質的レベルの思考に留まることによって容易に体制側の支持基盤になります。
そして体制側が給与格差と出世主義のコントロールの中にとりこまれます。
二つ目の問題は、労働組合の活動家は、その活動によって労働組合の中に自分の地位を確立します。
それは必要なことですし、献身的な労働組合の活動家のおかげで今日の労働者の地位が築かれてきました。
そのことによって彼らは尊敬を得ます。
ところが、この世に社会的地位をもつことで傲慢な気持ちが生ずるのを防ぐ理論と実践はありません。
「個」のレベルで肥大化しまい、「超個」すなわち謙虚な個への道を失います。
指導部の内部で、意見の違いを闘わせるのは重要ですが、論の違いと感情的もつれが重なって、「肥大化した個」のゆえに、団結すべき労働者階級は、協力から分裂へと進みます。
「肉の眼」「知の眼」に「観想の眼」を導入することによってその克服の道が開かれると私は考えます。
人々の出世と物欲をあおることを必要とする資本主義は、人間性の発達の妨げとなっています。
私たちは、マルクスの問題意識を「含んで超えて」、資本主義を超える新な社会への方途をさぐらなくてはなりません。
それは資本主義の達成した良きものを「含んで超える」未来でなくてはなりません。
サルカールは、進歩的社会主義(プラウト)としてその構想を示していますが、私たちは、ケン・ウィルバーのホロン論を活用して、同様の新たな未来への道を構想することができます。
ホロン論は、「個と共同性」のテーマについて、新たな地平を私たちに開いてくれます。
(7)ホロン論は、個と共同性の問題に新な地平を開く
(ア)ケン・ウィルバーのホロン論
ケン・ウィルバーのホロンについて正確な詳しいことは『進化の構造(1)』春秋社の最初の部分にまかせるとして、まず簡単にウィルバーの考えを説明します。
まず、ウィルバーは心の内側と外側は統一的にみてゆかねばならないといいます。
心の内側、たとえば文化論や心理学は、リアリティの一面にすぎないといいます。
心の外側、たとえば、脳の神経伝達物質、あるいは経済は、リアリティの一面にすぎません。
内側と外側を統一的にみてゆかねば、リアリティに迫ることはできないとします。
まったく独立して存在している個はこの世に一切ありません。
集合体として個々の存在が成立しています。
他の関連、集合体とのかかわり抜きに、個々の存在を考察しても、それは部分的真理を解明するにすぎません。
内と外、個と集合体、この四つを統合的に分析することを彼は「四象限統合アプローチ」と呼びます。
そして、四象限は一つのものとして、階層的に発達を遂げてゆきます。
発達のスピードは異なっても、超えるべき発達の波を飛び越えることはできません。
この発達のレベルに応じたアプローチが必要です。
それを「全レベルアプローチ」と呼びます。
ケン・ウィルバーが主張しているのは「全象限全レベルアプローチ」です。
個は、一定の発達段階の中に、そして四象限の中に存在します。
そこから離れて存在しえません。
一例を考えてみます。全宇宙に水素、ヘリウムが充満しました。
衝突と結合の中でさらに原子が成立し、分子が成立しました。
すなわち気体、液体、固体が成立しました。
そして分子から細胞が成立しました。
分子は原子を「含んで超えた」存在です
。細胞は分子を「含んで超えた」存在です。
細胞が人体の器官を形成します。
器官は「細胞」を含んで超えた存在です。
人体は「器官と細胞」を「含んで超えた」存在です。
ホロンとは、「個体」としてのエイジェンシー(自律性)をもち、他のホロンとのコミュニオン(共同性)をもっている単位をさします。
原子は、自律性と自己決定権をもって回転し、その引力で他の原子との一定の関係に入ります。
原子の集合体としてより高次のホロンである分子が生じます。
分子は、自律性と自己決定権を行使しながら他の分子と連携し、上位ホロンである細胞を形成しています。
それぞれのホロンレベルで、個体としてのエイジェンシー(自律性)とコミュニオン(共同性)の能力を持ちます。
ホロンとは、(部分/全体)という意味で、下位ホロンに対しては一つの統合された全体としての個体であり、上位ホロンを構成する部分です。
この宇宙にあるもの一切がホロン(部分/全体)として存在します。
部分だけであるものも存在しませんし、全体だけであるものも存在しません。
全体と部分、すなわちエイジェンシー(自律性)とコミュニオン(共同性)のバランスがくずれる時、病的になります。
発達途上での健全な範囲のバランスのくずれをウィルバーは「分化」といい、病的なバランスのくずれを「分離」と呼びます。
原子⇒分子⇒細胞⇒器官⇒人体⇒と例にあげたように、天地万物一切のものは階層構造(ヒエラルヒー)の中にあります。
しかし、これは従来、考えられていたようなヒエラルヒーではありません。
ヒエラルヒーとは上から下への命令構造としての階層性をさします。
しかし、細胞は個々の分子に命令しませんし、分子は、原子に命令しません。
逆に下から階層性は構成されてきました。細胞よりも分子の方が、分子よりも原子の方が先に出現しています。
「こうしてケストラーは、すべての複雑な階層はホロン、または増大する全体性から成立していることを指摘した後、階層性(ヒエラルヒー)という言葉は、正しくはホラーキー(ホロン階層性)と呼ぶべきであると考えたのだった。
彼はまったく正しい。
したがって以後、私も存在の偉大な連鎖、ないし階層を呼ぶ時、ホロン階層と呼ぶことにしたい」
ケン・ウィルバー『進化の構造』春秋社、61ページ。
したがって、ホラーキー階層性においては、下位ホロンは、上位ホロンの命令ではなく、自律性をもって、自決権をもって活動し、かつ、同じホロンレベルと協同し、連携して上位ホロンを構成します。
(イ)個人ホロンの上位ホロンとしての家族と職場のホロン
個人をホロンしましょう。
個々の人間は、生命の生産と再生産の場、すなわち家庭と生産の場である職場に属して活動します。
自営農民や小商店主など、家庭の単位と生産の単位が合致するもケースがありますが、ここでは、家庭と職場が分離している場合を例に考えてみます。
職場では個別で働く場合もありますが、チームで働く場合もあります。
チームは部署に属します。部署の上に役員会があり、企業全体を統括します。
企業は、同じ業界、他業種、行政などとの関連に入ります。
個人の従業員が一つのホロンレベルです。
チームもホロンです。部署もホロンです。
企業全体もホロンです。
業界全体もホロンです。
個人として自律しながら、協同で仕事をします。
その協同の中でチームの仕事をします。
チームとして仕事する中で意識の統合がなされてチームとしての意思と統合された意識が成立します。
チームは他のチームとの協同の中で仕事をします。
協同で仕事をする中で、チームを統括する部署の意識が成立します。
部署は、自律的に仕事をします。
他の部署との協同で仕事をする中で統合された意識が成立します。
すなわち、各ホロンレベルにおいて個と共同性の問題があります。
各レベルで、個として統合され、個として確立しているか、そして他の個と協力関係がうまくいっているか。各レベルでエイジェンシーとコミュニオンの問題が問われてきます。
各ホロンレベルでのエイジェンシー(自己決定権をもつ自律性)とコミニュオン(協同)のバランスが大切です。
各ホロンレベルにおけるホロンは、完全にエイジェンシーのみであることはありえません。
部分としてしか存在しえませんから、上位ホロン(全体)の情報を受けて、自律的に活動してゆきます。
バランスのとれた個と共同性は各ホロンレベルにおいて、重層的に実現されなくはなりません。
P.R.サルカールの進歩的社会主義(プラウト)においては、このことは経済民主主義として提起されています。
そして大企業は協同組合経営になります。
そして上意下達のヒエラルヒー構造ではなく、ホロン構造となります。
当面の提案の一つは、企業は、次の会社を世話するまで社員の首を切れない法律を創ることです。
労働者は家庭にも属しています。
家庭も一つのホロンです。個々人がともに生活する中で家庭としての統合された意識が成立します。
家庭が集まって、村や町の地域ブロックが成立します。
その上に連合した地域があり、市や郡レベル、県レベルの地域が成立します。
三割自治と呼ばれて、国が地域を支配するシステムがあります。
下位ホロンが自己決定権をもち、他のホロンと協力して上位ホロンを形成するというシステムになるべきです。
すなわち下からピラミッド状に積み上げてゆくシステムです。
P.R.サルカールの進歩的社会主義(プラウト)においては、このことは、地域経済圏(ユニット)という構想の中で述べられています。
下位経済ブロックが、地域の短期の経済計画を策定する権利をもちます。
そして他の下位ブロックと調整してゆきます。
下から上へと経済計画がのぼってゆきながらより広範囲な範囲で調整されてゆきます。
ソ連社会主義では、中央のモスクワが地方の経済開発の決定権をもっていました。
アメリカ資本主義では、ニューヨークにある本社が、遠く離れた地域の支店の経済活動の決定権をもちます。
いずれも、地域の住民に自分たちの住む地域について決定権をもちません。
サルカールの進歩的社会主義の理論は、地域の人々が下から決定権をもつホラーキー構造をめざすものです。
行政単位のホロンレベルを考察すると、町や市の上に県のホロンレベルがあります。
県のホロンレベルの上に国のホロンレベルがあります。
原子の活動を分子が命令しないように、分子の活動を細胞が命令しないように、国も県や市の活動を命令するものではあってはなりません。
ホロンは、どこまでいってもホロンです。
国も最終のホロンではありません。
国を最終のホロンとして教育の最高の目標とするものがナショナリスト(民族主義者、国家主義者)ですが、国も諸国の一つです。
したがって、全人類を包含した世界連邦政府まで達して、個人を再下部ホロンとした最高レベルのホロンが成立します。
世界連邦政府まで成立しても、組織はヒエラルヒーではありません。
ホラーキー構造として、下部ホロンが自己決定権、自律性をもって活動し、他ホロンとの協同で上位ホロンを成立させます。
個々人の帰属意識は、特定のホロンレベルに特化されたものではなくなります。
ある特定のホロンレベルが肥大化するならば、病的になります。
ナショナリストは、国レベルのホロンを肥大化させようと試みます。
なお、デヴィッド・コーテンは、多国籍企業が、企業ホロンレベルでのガン細胞の役割を果たしているので健全な細胞に分化させなくてはならないと言います。
どの領域、どのレベルにおいても、ホロンが肥大化しすぎるならば、病的になり、問題をひきおこします。職場の中で特定人物がボス的になることも、ホロンの肥大化です。
(ウ)私たちはホラーキー階層構造をめざす
このホラーキー階層性の概念がでるまで、個と共同性のテーマは階層性の中で論じられることはありませんでした。
ヒエラルヒー階層性は、共同性の名をもって上位が下位の個を支配します。
今日、消費文化が物欲に人々を導く中で、個の未発達な低次のレベルで、個が肥大化することで、様々な反社会的行為や非社会的な行為が生じています。
地下鉄でつばを平気で吐く人、電車の中での化粧や携帯電話、成人式での私語や身勝手な行動などなど、そうした問題が背景に共同性の育成の側面が課題にのぼっています。
それを愛国心教育という上位ホロンへの帰属意識とヒエラルヒー階層構造の強化によって解決しようという動きが強まっています。
これは、下位ホロンの共同性の強化をするのではなく、下位ホロンの自律性をつぶすことで、エイジェンシー(自律)とコミニュオン(協同)のバランスを低次のレベルで実現しようとすることです。
そして、上位特定レベルのホロンの肥大化自体も新たな病的な症状を引き起こすことになります。
ホラーキー階層構造が天地万物の理であるのに、ヒエラルヒー構造は、そこからはずれていますから、上位ホロンレベルにおいても、下位ホロンレベルにおいても問題をひきおこします。
私たちは、ホラーキー階層構造の実現に向かって活動してゆくべきだと思います。
職場では、個人として自律するとともにチームとして部署としての統合した意識が成立するように協力してゆかなくてはなりません。
それぞれのチーム、部署の統合された意思が尊重されるような運営を勝ち取ってゆかなくてはなりません。
労働組合は、それぞれのホロンレベルの自律性(エイジェンシー)の側面、自己決定権の側面が剥奪されないように要求して、エイジェンシーとコミュニオンのバランスの維持を確保するために闘わなくてはなりません。
さらに「次の職場を世話するまで首を切れない」という法律を実現することで、社会における最下部のホロンを形成する諸個人の不安を除去しなくてはなりません。
首切りの不安は、エイジェンシーとコミュニオンのバランスを崩します。
私たちは、天地万物の理であるホラーキー構造の社会の確立をめざすべきだと考えます。
ここに個と共同性の問題は、高次のレベルでの解決を実現します。
まとめ スピリチュアリストは、個として自立した闘いを放棄しない
超個の中に自らを確立するスピリチュアリティは、この世から離れところに人生の目標をもち、保守的で権力に従順に従い、非社会的であることを推進する思想のイメージがあります。
しかし、サルカールは、スピリチュアリティの高い人間は人類の福利のために闘ったと言い、そうした人間をサドヴィプラ(レベルの高い知識人、革命的スピリチュアリスト)と呼びました。
そして自分自身も、1960年ころ、インドで言語ナショリズムが高まり、分裂の危機が生じた時、ナショナリズムを批判し、インド統一を守る立場からの呼びかけをおこなっています。
決して、現実の政治、社会、経済から離れたところに人生を設定しませんでした。
ケン・ウィルバーも同様の思想を語っています。
一つ目に、アメリカでは声を上げる道徳的勇気を失うことがスピリチュアリティと勘違いしているという指摘です。
「彼らが論争的であったのは、まさに彼らがチョギャム・トゥルンパの言う『慈悲』と『愚か者の慈悲』の違いを知っていたからである。
これはポリティカルにはコレクストな(政治的にお上品なことしか言わない)アメリカ人には、もっとも飲み込みにくい教えである。
アメリカでは愚か者の慈悲-違いを見抜く智恵を放棄すること、その結果、道徳的な声をあげる勇気を失うことが-があまりにしばしば、スピリチュアリティと同一視されているからである」
ケン・ウィルバー『統合心理学』394ページ
二つ目に、無選択的な意識、すなわち無我の境地に達することを判断の放棄と勘違いしている。
深いレベルに達した意識からは、レベルの高い判断が湧き上がるという指摘です。
「人々は、無選択的な意識を何も判断しないことと取り違えている。
むしろ、無選択的な意識というのは、判断ないし、無判断が状況に応じて適切に生起することを許す、ということである。
なぜ、多くの偉大なスピリチュアルな哲学者が、時に信じがたいほどに激しく論争的であったかという理由は、まさにここにある。
プロティノスがあまりにも激しく占星学者たちを攻撃し、・・・
さらにプロティノスはグノーシス派を呵責なく切り裂き、彼らは神性について語る権利さえ持たぬ、としたのである」
同上書395ページ
第三に、真のスピリチュアリストは、意識の深いレベルから湧き上がる分別智をもって論争に参加するという指摘です。
「私は、こんなにまで激しく論争的であるような人は、あまりに悟っているとは言えないのではないかと考えたこともあった。
しかし、今はまったく逆であると理解している。
私たちは、本当のスピリチュアリティはこうした論争を回避すべきだと、信じがちであるが、実際は逆に、深度を判断する力の顕現として、すなわち分別智の顕現として、真のスピリチュアリティは情熱的に論争に参加する」
同上書395ページ
第四に、それは個人的なレベルからではなく、より深い普遍的レベルの集合的福利のための全存在をかけた勇気ある心の叫びだという指摘です。
ここには「超個」まで達した高いレベルの「個」があります。
「それは、心の中から湧き上がる、鋭い叫び声である。
神経症を行動化することは、何の努力もいらない。
だが、立ち上がって全存在をかけ、心の叫びを上げることは、非常な勇気を要する。
私が、先に言及した哲学者や聖者を尊敬するようになったのは、彼らがそのすばらしい判断を、すべての力を使って残していってくれたからである。(中略)
自分たちがおかれている状況のひどさを何もかもはっきり見ている人は、数多く存在する。
彼らはプライベートな状況ではそのことについて話をする。
彼らは私にいつもそのことについて語る。
反動的で、反進歩的で、退行的な雲が全分野を覆いつつあることを彼らは、心底心配している。
しかし、ほとんどの人は立ち上がって声を上げることをしない。
なぜなら、カウンターカルチャーの秘密警察が制裁や断罪を下すべく、いつも待ち受けているからである」
同上書396ページ。
これらのケン・ウィルバーの指摘は、道徳的な声を上げる勇気を失うことがスピリチュアリティの高さではないこと。
逆に、今日、全分野を覆いつつある反動的で、反進歩的で、退行的な雲に対して、立ち上がって全存在をかけ、心の叫びを上げること、そして明瞭に自らの深い判断力、分別智の顕現を示すこと、それが本物のスピリチュアリストの証だというのです。
この「超個」は、「個の確立と共同性」の最高の次元まで達しています。
H.P. of socialist earth government (社会主義地球政府のH.P.)Morimoto is only true Marxist in 20th century.
Mitsuki's life is deepening true Marxism.
この論文は,みつきの守本順一郎の思想史研究から受け取った個と共同性のテーマを最高のレベルまで高めた生涯にわたる思索の結果をまとめたものです。
守本順一郎は20世紀の唯一の真のマルクス主義者です。
みつきの生涯は真のマルクス主義を深めつづけたものだったのです。
まえがき
拝啓
先生の以下のご指摘はもっともだと思います。
「サイードや工藤庸子に言わせると、マルクスも『オリエンタリスト』(英仏を筆頭とする帝国主義者がアジア等の異文化・異文明を『野蛮』として奇異な目で見る観点の人たち)の最たる一員です。
『まず西欧的(あるいは一神教的?)な個の自立、しかる後に共同』で良いのかどうか、問題だと思います」
個と集合体との関係性について、私の考えを説明しないと誤解されると思いますので、少し詳しく論じさせてもらいます。
(1)「必須の通過点」としての個の確立の意味
資本の本源的蓄積過程で小農民や職人が土地などの生産手段を奪われて、生産手段を所有する資本家に雇われるしか、生きてゆく道がなくなります。
これは資本主義が発展する過程では、世界中に見られる現象です。
資本主義の発展の中で機械の一部となって働かされる労働者は、もはや職人や農民であった時代にもち得たような主体性はありません。
マルクスは「疎外された労働」と呼びましたが、「疎外された労働」から解放されるためには、労働者たちが、働く職場の主人公とならなくなはなりません。
後にマルクスの「社会主義」理論は、生産手段の国有化として結実してしまいましたが、本来のマルクスの問題意識は、労働者たちが働く場で主人公になる。
すなわち主体性を回復することにあったとおもいます。
(P.R.サルカールは、マルクスのこの問題意識を継承し、経済民主主義を基本とする進歩的社会主義(プラウト)の理論を創始し、適切に解答を与えていると考えます。
さらにケン・ウィルバーのホロンとホラーキーの理論を用いれば、結局のところ、サルカールと類似の理論を創造することができます。
これについては、後で説明します)
「必須の通過点」としての個の確立を論じたのは、西洋で発達した資本主義システムとその文明を即美化するためではありません。
資本主義システムは、個の主体性の確立を奪うものだからです。
しかしながら、本源的蓄積過程、すなわち生産手段を所有している資本家に雇われるしかない多数の労働者が農村から析出される時点において、農民の主体性のレベルがどの程度あったかは、労働者階級に組み込まれた彼らが主体性を回復するために団結して闘う意欲に関連してきます。
資本家の側に組み込まれて、経営の発展や技術の発展に尽くす能力にも、本源的蓄積過程で労働者に転化する農民がどの程度の主体性をもっていたかは重要です。
実際、資本主義の発展過程を見ても、独立した小農民レベルに達した英米仏、ドイツの西側地域、それに対して地主制のあった東欧地域、日本も地主制があり、共同体規制はあるけれども、経営単位は小農民家族にありました。
私が調べていたイランのライーヤット(農民)は、経営単位は農民家族にありませんでした。
ラテン・アメリカのラティフンデオ(大土地所有制)も経営単位が農民家族になかったとおもいます。
朝鮮、中国、東南アジア地域での資本主義の発展が進んでいますが、経営単位は農民家族にあります。
これは実証の問題ですが、資本家と労働者が形成されてゆくに際して、彼らの個としての主体性のレベルが、影響してゆくだろうことは確実です。
そして地主支配からも解放されて、完全に自らの生活の主人公となった独立自営農民のレベルの主体性を「必須の通過点」という考えに共鳴します。
主体性をもった彼らのつくりだした文化の質は、次の資本主義段階で主体性を奪われた状況に対して抵抗する心を激励してゆくものとなるはずです。
(もちろん、一つの要因としてです。それが要因のすべてだと言っているのではありません)
たとえば、人気番組の水戸黄門で、繰り返し、権力者によって問題を解決してもらうという心性を教育されつづけている私たちの社会とはちがって、「必須の通過点」を経た文化は、水戸黄門のような外からやってきた善き権力者に問題の解決を期待するのではなく、その地域の人々が力をあわせることによって問題を解決する心性を育む文化を継承しているはずです。
(2)守本順一郎の思想史研究の意義
こうした私の問題意識は、故守本順一郎(元名古屋大学の思想史研究者)の思想史研究によります。
簡単に手に入る本は『日本思想史、上中下』新日本新書です。
彼は、マルクスの資本論に『個』としての自立が『必須の通過点』であるとしたことにならって、思想史における「個」の確立まで前近代史の思想史を研究して、この世を去りました。
その研究は、決して、「西洋的個の自立、しかる後、共同」という文脈からではありません。
まさしくそうした西洋は個が自立しているという単純な考えを批判するためでした。
「ヨーロッパの近代資本主義=帝国主義が、広大な範域を占める東洋諸国に資本主義=帝国主義的衝撃(インパクト)を与えるまで、たしかに東洋の世界は、外貌的には専制的支配の世界であった。
だが、上述のように、ヨーロッパ的精神の立場から東洋を停滞的社会として捉えることは、既に(自由)の精神を展開させえたと自負するヨーロッパ精神にとっては、そのような東洋の内容把握も、外からの、いわば好奇心から、瞥見にすぎなかった。・・・
かくして、古代から近代資本主義の時代、さらにいえば、最近の帝国主義段階に至るまで、ヨーロッパの精神は、東洋の本質をその内的発展において探るべき必然性を自己の裡にもたなかったといえるであろう」
守本順一郎『東洋政治思想史研究』未來社、1967年、10、11ページ
彼は、西洋思想、インド思想、中国思想について、個と共同性(ケン・ウィルバー的にいうとエイジェンシーとコミュニオン)の構造を発展のありさまを見事に普遍的に描きだしています。
共同体に埋没した個から、すなわちコミニュオン優位型から、次第に個が力をましてゆく様子を普遍的に、かつ地域的特性を描きだしながら、論じています。
前近代思想を論じていますが、私は、その中に自立した個の連合としての未来社会論を読み取っています。
そして自立個の成立は「必須の通過点」です。
もちろん、一人だけで成り立つような個はこの宇宙のどこにも存在しえません。
自立した個といえども、他者との関係性を前提としてのことはもちろんです。
具体的なイメージは、たとえば独立自営農民として「いつ、何の種をまき、どういう肥料をやり、いつ、刈り取り、市場に出すか」などについて自己決定権をもつということです。
地主や共同体の規制から自由に決定できるということです。
たしか、マルクスは、資本論の中で14世紀のイギリスに広範にヨーマンリーが成立し、彼らは、非常に狭い世界観の中ではあるけれども、独立した小宇宙をつくっていたことなどを論じていたとおもいます。
自己決定権をもっていた小農民が、資本主義の発展の中で、生産手段を奪われ、自己決定権を失った労働者として働かされるようになります。
そして資本主義が発達させた生産手段を労働者たちがわがものとして、生産における自己決定権を回復します。
これが資本論の論理でした。
つまり、主体的な個が協同の上に成立するのです。
この個とは共同の中に埋没する前近代的な個であってはなりません。
ソ連、中国、北朝鮮に、社会主義と名付けた統制経済が登場しましたが、それは集団に埋没した前近代的な個を前提としていました。
それは、「必須の通過点」として個の自立を経ずに、上から共同を押しつけた悲劇?でした。
マルクスのイメージはどう考えても、独立した生産者が、いったん生産手段を奪われる資本主義がやってくる。
そこでその生産手段をふたたびわがものにするというものです。
つまり自立した「個」を前提としているのです。
それは経済民主主義でもあります。
それなしには、全体主義や専制支配となってしまいます。
その意味で「自立した個」の成立は必須の通過点として、社会の前進の上でも個人の成長の上でも必要なことだと私は考えています。
(サルカールの進歩的社会主義(プラウト)は、まさしく、主体的な個の協同として、協同組合を基本とした組み立ての社会を構想しています。
そして経済民主主義を主張しています。
マルクスのもともとの労働者解放の問題意識を正当に継承し、その解決の展望をあたえているように私はみえます)
(3)一神教世界での個の発達
経済的側面から、個の確立という「必須の通過点」について述べました。
心の外側は内側に対応しています。
今度は内側を考えてみましょう。
守本順一郎は、一神教世界だから、個が確立したような短絡的な見方はしていません。
簡単に言います。
ギリシャ・ローマ(古典古代)の原始キリスト教段階では、奴隷は、この世で個として認められません。
死んで天国に行って救われます。
中世カトリシズム段階では、個はこの世で人間として認められますが、神に近い人間と神から遠い人間、人間以外の異端者や魔女というふうに位階制(身分制)が形成されます。
教会は高く天(神)に向かってそびえたちます。
個が自立できない背後には、領主支配と共同体規制の中で個別家族が成立するという事情が対応しています。
次にプロテスタンチズムがきます。
個と神とは直接につながります。
すなわち個は神の前で平等になります。
勤労してもうけることは神を讃えることになりますから、資本主義が発展します。
資本主義の発展の中で、個の自立はくずれてゆきます。
少し、私の解釈が加わっていますが、一神教世界でも歴史的な展開があったし、私たちの多神教世界でも歴史的な展開がありました。
したがって、言いたいことは、一神教的な個の自立を経たらいいという単純なことではないのです。
(4)内的世界でも重要な個の確立と自己決定権
依然として「必須の通過点」としての個の確立は、つまり確立した個の連合への道は私たちの社会の課題であるように思えます。
ヨーマンリーを例にとりましたが、知的世界でも「自分の研究畑で何をどのように研究するか」について自己決定権があり、その連合としてのアカデミズムの世界が発展すべきだとおもいます。
しかし、昨今の流れをみてみますと、政界や財界に学問界が従属しつつあるようにみえます。
本当に学者が自由に自分の畑で何をどのように研究するかについて自己決定権を維持できているのかが問題だとおもいます。
もちろん理科系の学問など現実の産業界との関係を軽視することができないのはよくわかりますが、たとえば、食品添加物の心と身体におよぼす害にいて研究しようとすると産業界がバックアップしないし、抑圧してくるだろうということは素人でもよくわかります。
学問界と産業界との関係ではありませんが、最近、人気があったテレビ番組「白い巨頭」では、江口洋介扮する医者が、本当のことを証言したら、妻への「世間」(大学教授の妻の会)から圧力がかかる様子を描いていました。
江口洋介扮する医者は、大学を追われて、自分の研究テーマが継続できませんでした。
そこまでのことはないにしても、今日も似たようなことがありうることは予想できます。
「自立した個の協同」というテーマは、今日のテーマでもあります。
個が自己決定権をもつことができるということを前提とした協同を実現することは、たいへん重要なことです。
それなしの協調は、容易に「体制順応型優等生」の協調になります。
洗練はされていても実質的には、個が集団に埋没した共同体です。
上からの支配を容易に許してしまいます。
内面的な側面について、さらに論じますと、理論と実践の統一は、個としての主体性の問題でもあります。
理論信仰になって、ある図式や理論的枠組みを、リアリティをより深く認識するために使うのではなく、理論自体を理解するために使う。
ここには個としての主体性はありません。
逆に理論を軽視して、実践だけを追求することは、暗に、その実践を指示しているもののいいなりになってしまいます。
どちらにしても、個は流されてゆきます。
この問題は日本の教育にもあるとおもいます。
優等生は、教えたことをそのまま受け入れて、記憶して、答案に書きます。
教えられたことをリアリティによって検証する実践にあたるものがありません。
だから教えられたことを真の意味で発展させることができません。
そういう優等生が、教育の仕事についても、容易に上から点数をつける制度である「評価・育成システム」の支配の目にからめとられ、行政からの採点に左右されるだろうとおもいます。
実践と理論を車の両輪のようにして自分の教育実践を発達させるスタイルの主体性をもったものはわずかしかでてこないでしょう。
調べてみると「優等生」の意味内容を含むものは英語の辞書にはありませんでした。
個の主体性をもった優秀な人物は、日本語では優等生とはいわないとおもいます。
盛んに教育界で、「個性」尊重とか多様化とかいいます。
私は多様性の尊重は、根源が一であるという意識、多様性の中に自分があるという意識が同時に育まれるならば、価値あることだと思います。
多様性の尊重の側面だけが推進され、自分にとって多様な他者という認識に留まるならば、自立した個(多)の連携(一)には進みません。
そして「個性」尊重と「個の確立」とは別のことです。
個性の尊重自体が個の確立に導くわけではありません。
個の確立、個の主体性の育成には、自分が耕す畑をもち、自己決定を行使することが重要です。
主体性は、自分の担当領域を与え、自己決定権を与えなくてはでてきません。
他人を利用しよう、操作しようという意図をもっている人間は、それを妨害してくるとおもいます。
(5)内面世界での個の確立を必須の通過点として論じはじめたケン・ウィルバー
ケン・ウィルバーは、『統合心理学』春秋社、において、個人の内面の発達においても、言葉は違いますが、事実上、個の確立を必須の通過点として強調しはじめています。
そしてトランスパーソナル心理学の理論家の一員であった段階から、まったく新しい人類的な思想の提出者となりつつあります。
彼は、偉大な叡知の伝統の目立つ欠陥に眼をふさぐことなく、その欠陥をとりあげなくてはならないと述べ、その欠陥の一つとして、「個」を消すことには導くが、「個」の確立に導かないことをあげています。
「強い安定した自我」の確立を人間発達の必須の通過点としているのです。
「偉大な観想的な伝統は、人間の成長の、心的で自我的なモードから超・心的でスピリチュアルなモードへの移行の洞察については非常にすぐれている。
しかし、心的・自我的なレベルへ達するまでの理解に関しては、非常に弱いものがあった。
ジャック・エンゲラーはいみじくも言っている。
「誰でもない、無の人になるためには、その前に誰かにならなくてはならない」(無私の前に私が来なければならない)強い安定した自我をもってはじめてそれを超越することができるのである。
偉大な叡知の伝統は、後の部分には見事に成功しているが、後の部分にはみじめに失敗しているのである」
ケン・ウィルバー著『統合心理学』春秋社、2004年、49ページ。
なお、叡知の伝統とか、観想の伝統というものは、キリスト教、仏教、イスラム教などの宗教的伝統の黙想的な部分をさしています。
個と集合体とのかかわりのテーマを内面的な発達の領域で見た場合、私たちの社会が直面しているのは、肥大化した個です。
お金や出世でコントロールするシステム、消費文化のコマーシャル、それは、物質的領域への我欲の肥大化です。
それは、心の奥に満たされない渇望を生みます。
癒しや仏教ブームの背景にあるものだとおもいます。
人権や差別反対のリベラリズムは、継承してゆかねばなりませんが、この満たされない渇望に対しては無力です。
より高次の渇望に組み替えてゆく以外に道はありません。
それは個を「含んで超える」道に解決があります。
「超える」個ですから、「超個」=トランスパーソナルです。
それを提起しているのがケン・ウィルバーです。
宗教の中の黙想的伝統は、「人間はパンのみにて生きるにあらず」と物的欲望をより高次なスピリチュアルな欲望に変える力をもっています。
しかし、個を消滅させる導き、すなわち個を超える導きには強いが、個を確立する点で弱いといいます。
それは専制的な上から支配する社会システムを容易に受け入れる人々を生み出します。
真にトランス、すなわち個を「含んで超える」ものでなくはなりません。
(そして二つ目の叡知の伝統の弱点として、それがまったく社会経済的側面を問題にしない点をあげています。
このことが、宗教が、保守的な人々、上からヒエラルヒー的に支配される社会システムを容易に受けいれる人々を数多く生み出し、リベラリズムに敵対するものとなっている背景にあるとウィルバーは考えます)
そして、トランスパーソナル心理学の人々とかつての自分は、「個」として確立する以前の「前個」を「超個」と勘違いしているとして前個⇒個⇒超個、すなわち「個」の確立を必須の通過点とすることを個人の内面の発達の上でも重視する立場を論じています。(同上書263ページ)
ケン・ウィルバーは、「自分の究極の関心事」の深まりと広がりの発展をスピリチュアリティの発達ラインとしています。
自分のことだけに関心がある領域から、分別のある理性の段階に達するのが個の段階です。
そして全人類的な運命が自己の関心事までに達した段階は、超個の高い段階に達しています。
スピリチュアリティの発達における「超個」とは現世から去ることではなくて、現世を「含んで超える」深まりをもつことです。
そして「自立した個」「主体的な個」を「含んで」超えていることです。
したがって、「超個」に発達した人間が増えれば、増えるほど、「自立した個」の共同、連携が発達してゆきます。
(6)マルクスの資本主義批判の限界
人々の出世と物欲をあおることを、今日の資本主義はその存在の必要条件としています。
それは人々を「超個」には導きません。自立した「個」のレベルの人々も出世競争の中にまきこまれ、この世での高い社会的地位の確立に執着します。
「前個」のレベルの人々もゆがめられてゆきます。
そこからスピリチュアリティへのがれようした一部の人々は、「個」としての主体性が、消滅させられ、崩壊させられてゆきます。
それがオウムです。
また宗教に走る人々も、ケン・ウィルバーの言うように、その保守性に取り込まれ、「前個」の受動性の中に取り込まれます。
したがって出世競争と物欲をあおる資本主義システム維持の基盤になります。
マルクスの資本主義批判は、労働者階級の資本家階級への階級闘争にあります。
まず労働条件などの向上の要求ために労働者階級として団結します。
そしてその中から育ってくる活動家は、労働者階級に奉仕することで無私の精神を発達させ、「個」の確立と「超個」に至ることになっています。
この場合、二つ問題があります。
労働運動の基盤は、労働条件の向上という物的要求に根ざします。
それは当然のことで、正しいことです。
しかし、その後に問題が二つあります。
その一つ目の問題は、その意識を階級意識に高めることを目標としています。
それは労働運動の発展、すなわち労働者階級の団結のためには必要なことですが、階級意識を普遍的意識に高める論理と実践が必要です。
物的要求を知的欲求にそしてそれを含んで超えたスピリチュアルな人間発達の要求に高める論理と実践です。
それがないと労働者は労働条件の向上を実現した後は、目標がなくなり、他民族の帝国主義的支配のイデオロギーにも容易に乗せられてゆきます。
逆に、もし、労働者階級が階級意識に目覚めなかったら、物質的レベルの思考に留まることによって容易に体制側の支持基盤になります。
そして体制側が給与格差と出世主義のコントロールの中にとりこまれます。
二つ目の問題は、労働組合の活動家は、その活動によって労働組合の中に自分の地位を確立します。
それは必要なことですし、献身的な労働組合の活動家のおかげで今日の労働者の地位が築かれてきました。
そのことによって彼らは尊敬を得ます。
ところが、この世に社会的地位をもつことで傲慢な気持ちが生ずるのを防ぐ理論と実践はありません。
「個」のレベルで肥大化しまい、「超個」すなわち謙虚な個への道を失います。
指導部の内部で、意見の違いを闘わせるのは重要ですが、論の違いと感情的もつれが重なって、「肥大化した個」のゆえに、団結すべき労働者階級は、協力から分裂へと進みます。
「肉の眼」「知の眼」に「観想の眼」を導入することによってその克服の道が開かれると私は考えます。
人々の出世と物欲をあおることを必要とする資本主義は、人間性の発達の妨げとなっています。
私たちは、マルクスの問題意識を「含んで超えて」、資本主義を超える新な社会への方途をさぐらなくてはなりません。
それは資本主義の達成した良きものを「含んで超える」未来でなくてはなりません。
サルカールは、進歩的社会主義(プラウト)としてその構想を示していますが、私たちは、ケン・ウィルバーのホロン論を活用して、同様の新たな未来への道を構想することができます。
ホロン論は、「個と共同性」のテーマについて、新たな地平を私たちに開いてくれます。
(7)ホロン論は、個と共同性の問題に新な地平を開く
(ア)ケン・ウィルバーのホロン論
ケン・ウィルバーのホロンについて正確な詳しいことは『進化の構造(1)』春秋社の最初の部分にまかせるとして、まず簡単にウィルバーの考えを説明します。
まず、ウィルバーは心の内側と外側は統一的にみてゆかねばならないといいます。
心の内側、たとえば文化論や心理学は、リアリティの一面にすぎないといいます。
心の外側、たとえば、脳の神経伝達物質、あるいは経済は、リアリティの一面にすぎません。
内側と外側を統一的にみてゆかねば、リアリティに迫ることはできないとします。
まったく独立して存在している個はこの世に一切ありません。
集合体として個々の存在が成立しています。
他の関連、集合体とのかかわり抜きに、個々の存在を考察しても、それは部分的真理を解明するにすぎません。
内と外、個と集合体、この四つを統合的に分析することを彼は「四象限統合アプローチ」と呼びます。
そして、四象限は一つのものとして、階層的に発達を遂げてゆきます。
発達のスピードは異なっても、超えるべき発達の波を飛び越えることはできません。
この発達のレベルに応じたアプローチが必要です。
それを「全レベルアプローチ」と呼びます。
ケン・ウィルバーが主張しているのは「全象限全レベルアプローチ」です。
個は、一定の発達段階の中に、そして四象限の中に存在します。
そこから離れて存在しえません。
一例を考えてみます。全宇宙に水素、ヘリウムが充満しました。
衝突と結合の中でさらに原子が成立し、分子が成立しました。
すなわち気体、液体、固体が成立しました。
そして分子から細胞が成立しました。
分子は原子を「含んで超えた」存在です
。細胞は分子を「含んで超えた」存在です。
細胞が人体の器官を形成します。
器官は「細胞」を含んで超えた存在です。
人体は「器官と細胞」を「含んで超えた」存在です。
ホロンとは、「個体」としてのエイジェンシー(自律性)をもち、他のホロンとのコミュニオン(共同性)をもっている単位をさします。
原子は、自律性と自己決定権をもって回転し、その引力で他の原子との一定の関係に入ります。
原子の集合体としてより高次のホロンである分子が生じます。
分子は、自律性と自己決定権を行使しながら他の分子と連携し、上位ホロンである細胞を形成しています。
それぞれのホロンレベルで、個体としてのエイジェンシー(自律性)とコミュニオン(共同性)の能力を持ちます。
ホロンとは、(部分/全体)という意味で、下位ホロンに対しては一つの統合された全体としての個体であり、上位ホロンを構成する部分です。
この宇宙にあるもの一切がホロン(部分/全体)として存在します。
部分だけであるものも存在しませんし、全体だけであるものも存在しません。
全体と部分、すなわちエイジェンシー(自律性)とコミュニオン(共同性)のバランスがくずれる時、病的になります。
発達途上での健全な範囲のバランスのくずれをウィルバーは「分化」といい、病的なバランスのくずれを「分離」と呼びます。
原子⇒分子⇒細胞⇒器官⇒人体⇒と例にあげたように、天地万物一切のものは階層構造(ヒエラルヒー)の中にあります。
しかし、これは従来、考えられていたようなヒエラルヒーではありません。
ヒエラルヒーとは上から下への命令構造としての階層性をさします。
しかし、細胞は個々の分子に命令しませんし、分子は、原子に命令しません。
逆に下から階層性は構成されてきました。細胞よりも分子の方が、分子よりも原子の方が先に出現しています。
「こうしてケストラーは、すべての複雑な階層はホロン、または増大する全体性から成立していることを指摘した後、階層性(ヒエラルヒー)という言葉は、正しくはホラーキー(ホロン階層性)と呼ぶべきであると考えたのだった。
彼はまったく正しい。
したがって以後、私も存在の偉大な連鎖、ないし階層を呼ぶ時、ホロン階層と呼ぶことにしたい」
ケン・ウィルバー『進化の構造』春秋社、61ページ。
したがって、ホラーキー階層性においては、下位ホロンは、上位ホロンの命令ではなく、自律性をもって、自決権をもって活動し、かつ、同じホロンレベルと協同し、連携して上位ホロンを構成します。
(イ)個人ホロンの上位ホロンとしての家族と職場のホロン
個人をホロンしましょう。
個々の人間は、生命の生産と再生産の場、すなわち家庭と生産の場である職場に属して活動します。
自営農民や小商店主など、家庭の単位と生産の単位が合致するもケースがありますが、ここでは、家庭と職場が分離している場合を例に考えてみます。
職場では個別で働く場合もありますが、チームで働く場合もあります。
チームは部署に属します。部署の上に役員会があり、企業全体を統括します。
企業は、同じ業界、他業種、行政などとの関連に入ります。
個人の従業員が一つのホロンレベルです。
チームもホロンです。部署もホロンです。
企業全体もホロンです。
業界全体もホロンです。
個人として自律しながら、協同で仕事をします。
その協同の中でチームの仕事をします。
チームとして仕事する中で意識の統合がなされてチームとしての意思と統合された意識が成立します。
チームは他のチームとの協同の中で仕事をします。
協同で仕事をする中で、チームを統括する部署の意識が成立します。
部署は、自律的に仕事をします。
他の部署との協同で仕事をする中で統合された意識が成立します。
すなわち、各ホロンレベルにおいて個と共同性の問題があります。
各レベルで、個として統合され、個として確立しているか、そして他の個と協力関係がうまくいっているか。各レベルでエイジェンシーとコミュニオンの問題が問われてきます。
各ホロンレベルでのエイジェンシー(自己決定権をもつ自律性)とコミニュオン(協同)のバランスが大切です。
各ホロンレベルにおけるホロンは、完全にエイジェンシーのみであることはありえません。
部分としてしか存在しえませんから、上位ホロン(全体)の情報を受けて、自律的に活動してゆきます。
バランスのとれた個と共同性は各ホロンレベルにおいて、重層的に実現されなくはなりません。
P.R.サルカールの進歩的社会主義(プラウト)においては、このことは経済民主主義として提起されています。
そして大企業は協同組合経営になります。
そして上意下達のヒエラルヒー構造ではなく、ホロン構造となります。
当面の提案の一つは、企業は、次の会社を世話するまで社員の首を切れない法律を創ることです。
労働者は家庭にも属しています。
家庭も一つのホロンです。個々人がともに生活する中で家庭としての統合された意識が成立します。
家庭が集まって、村や町の地域ブロックが成立します。
その上に連合した地域があり、市や郡レベル、県レベルの地域が成立します。
三割自治と呼ばれて、国が地域を支配するシステムがあります。
下位ホロンが自己決定権をもち、他のホロンと協力して上位ホロンを形成するというシステムになるべきです。
すなわち下からピラミッド状に積み上げてゆくシステムです。
P.R.サルカールの進歩的社会主義(プラウト)においては、このことは、地域経済圏(ユニット)という構想の中で述べられています。
下位経済ブロックが、地域の短期の経済計画を策定する権利をもちます。
そして他の下位ブロックと調整してゆきます。
下から上へと経済計画がのぼってゆきながらより広範囲な範囲で調整されてゆきます。
ソ連社会主義では、中央のモスクワが地方の経済開発の決定権をもっていました。
アメリカ資本主義では、ニューヨークにある本社が、遠く離れた地域の支店の経済活動の決定権をもちます。
いずれも、地域の住民に自分たちの住む地域について決定権をもちません。
サルカールの進歩的社会主義の理論は、地域の人々が下から決定権をもつホラーキー構造をめざすものです。
行政単位のホロンレベルを考察すると、町や市の上に県のホロンレベルがあります。
県のホロンレベルの上に国のホロンレベルがあります。
原子の活動を分子が命令しないように、分子の活動を細胞が命令しないように、国も県や市の活動を命令するものではあってはなりません。
ホロンは、どこまでいってもホロンです。
国も最終のホロンではありません。
国を最終のホロンとして教育の最高の目標とするものがナショナリスト(民族主義者、国家主義者)ですが、国も諸国の一つです。
したがって、全人類を包含した世界連邦政府まで達して、個人を再下部ホロンとした最高レベルのホロンが成立します。
世界連邦政府まで成立しても、組織はヒエラルヒーではありません。
ホラーキー構造として、下部ホロンが自己決定権、自律性をもって活動し、他ホロンとの協同で上位ホロンを成立させます。
個々人の帰属意識は、特定のホロンレベルに特化されたものではなくなります。
ある特定のホロンレベルが肥大化するならば、病的になります。
ナショナリストは、国レベルのホロンを肥大化させようと試みます。
なお、デヴィッド・コーテンは、多国籍企業が、企業ホロンレベルでのガン細胞の役割を果たしているので健全な細胞に分化させなくてはならないと言います。
どの領域、どのレベルにおいても、ホロンが肥大化しすぎるならば、病的になり、問題をひきおこします。職場の中で特定人物がボス的になることも、ホロンの肥大化です。
(ウ)私たちはホラーキー階層構造をめざす
このホラーキー階層性の概念がでるまで、個と共同性のテーマは階層性の中で論じられることはありませんでした。
ヒエラルヒー階層性は、共同性の名をもって上位が下位の個を支配します。
今日、消費文化が物欲に人々を導く中で、個の未発達な低次のレベルで、個が肥大化することで、様々な反社会的行為や非社会的な行為が生じています。
地下鉄でつばを平気で吐く人、電車の中での化粧や携帯電話、成人式での私語や身勝手な行動などなど、そうした問題が背景に共同性の育成の側面が課題にのぼっています。
それを愛国心教育という上位ホロンへの帰属意識とヒエラルヒー階層構造の強化によって解決しようという動きが強まっています。
これは、下位ホロンの共同性の強化をするのではなく、下位ホロンの自律性をつぶすことで、エイジェンシー(自律)とコミニュオン(協同)のバランスを低次のレベルで実現しようとすることです。
そして、上位特定レベルのホロンの肥大化自体も新たな病的な症状を引き起こすことになります。
ホラーキー階層構造が天地万物の理であるのに、ヒエラルヒー構造は、そこからはずれていますから、上位ホロンレベルにおいても、下位ホロンレベルにおいても問題をひきおこします。
私たちは、ホラーキー階層構造の実現に向かって活動してゆくべきだと思います。
職場では、個人として自律するとともにチームとして部署としての統合した意識が成立するように協力してゆかなくてはなりません。
それぞれのチーム、部署の統合された意思が尊重されるような運営を勝ち取ってゆかなくてはなりません。
労働組合は、それぞれのホロンレベルの自律性(エイジェンシー)の側面、自己決定権の側面が剥奪されないように要求して、エイジェンシーとコミュニオンのバランスの維持を確保するために闘わなくてはなりません。
さらに「次の職場を世話するまで首を切れない」という法律を実現することで、社会における最下部のホロンを形成する諸個人の不安を除去しなくてはなりません。
首切りの不安は、エイジェンシーとコミュニオンのバランスを崩します。
私たちは、天地万物の理であるホラーキー構造の社会の確立をめざすべきだと考えます。
ここに個と共同性の問題は、高次のレベルでの解決を実現します。
まとめ スピリチュアリストは、個として自立した闘いを放棄しない
超個の中に自らを確立するスピリチュアリティは、この世から離れところに人生の目標をもち、保守的で権力に従順に従い、非社会的であることを推進する思想のイメージがあります。
しかし、サルカールは、スピリチュアリティの高い人間は人類の福利のために闘ったと言い、そうした人間をサドヴィプラ(レベルの高い知識人、革命的スピリチュアリスト)と呼びました。
そして自分自身も、1960年ころ、インドで言語ナショリズムが高まり、分裂の危機が生じた時、ナショナリズムを批判し、インド統一を守る立場からの呼びかけをおこなっています。
決して、現実の政治、社会、経済から離れたところに人生を設定しませんでした。
ケン・ウィルバーも同様の思想を語っています。
一つ目に、アメリカでは声を上げる道徳的勇気を失うことがスピリチュアリティと勘違いしているという指摘です。
「彼らが論争的であったのは、まさに彼らがチョギャム・トゥルンパの言う『慈悲』と『愚か者の慈悲』の違いを知っていたからである。
これはポリティカルにはコレクストな(政治的にお上品なことしか言わない)アメリカ人には、もっとも飲み込みにくい教えである。
アメリカでは愚か者の慈悲-違いを見抜く智恵を放棄すること、その結果、道徳的な声をあげる勇気を失うことが-があまりにしばしば、スピリチュアリティと同一視されているからである」
ケン・ウィルバー『統合心理学』394ページ
二つ目に、無選択的な意識、すなわち無我の境地に達することを判断の放棄と勘違いしている。
深いレベルに達した意識からは、レベルの高い判断が湧き上がるという指摘です。
「人々は、無選択的な意識を何も判断しないことと取り違えている。
むしろ、無選択的な意識というのは、判断ないし、無判断が状況に応じて適切に生起することを許す、ということである。
なぜ、多くの偉大なスピリチュアルな哲学者が、時に信じがたいほどに激しく論争的であったかという理由は、まさにここにある。
プロティノスがあまりにも激しく占星学者たちを攻撃し、・・・
さらにプロティノスはグノーシス派を呵責なく切り裂き、彼らは神性について語る権利さえ持たぬ、としたのである」
同上書395ページ
第三に、真のスピリチュアリストは、意識の深いレベルから湧き上がる分別智をもって論争に参加するという指摘です。
「私は、こんなにまで激しく論争的であるような人は、あまりに悟っているとは言えないのではないかと考えたこともあった。
しかし、今はまったく逆であると理解している。
私たちは、本当のスピリチュアリティはこうした論争を回避すべきだと、信じがちであるが、実際は逆に、深度を判断する力の顕現として、すなわち分別智の顕現として、真のスピリチュアリティは情熱的に論争に参加する」
同上書395ページ
第四に、それは個人的なレベルからではなく、より深い普遍的レベルの集合的福利のための全存在をかけた勇気ある心の叫びだという指摘です。
ここには「超個」まで達した高いレベルの「個」があります。
「それは、心の中から湧き上がる、鋭い叫び声である。
神経症を行動化することは、何の努力もいらない。
だが、立ち上がって全存在をかけ、心の叫びを上げることは、非常な勇気を要する。
私が、先に言及した哲学者や聖者を尊敬するようになったのは、彼らがそのすばらしい判断を、すべての力を使って残していってくれたからである。(中略)
自分たちがおかれている状況のひどさを何もかもはっきり見ている人は、数多く存在する。
彼らはプライベートな状況ではそのことについて話をする。
彼らは私にいつもそのことについて語る。
反動的で、反進歩的で、退行的な雲が全分野を覆いつつあることを彼らは、心底心配している。
しかし、ほとんどの人は立ち上がって声を上げることをしない。
なぜなら、カウンターカルチャーの秘密警察が制裁や断罪を下すべく、いつも待ち受けているからである」
同上書396ページ。
これらのケン・ウィルバーの指摘は、道徳的な声を上げる勇気を失うことがスピリチュアリティの高さではないこと。
逆に、今日、全分野を覆いつつある反動的で、反進歩的で、退行的な雲に対して、立ち上がって全存在をかけ、心の叫びを上げること、そして明瞭に自らの深い判断力、分別智の顕現を示すこと、それが本物のスピリチュアリストの証だというのです。
この「超個」は、「個の確立と共同性」の最高の次元まで達しています。
appeal of gods of star
all H.P. of project of Heaven and gods